

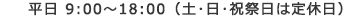

|
今日(一月十三日)でイスラエルに来てからちょうど百日を迎えました。僕の住むベエル・シェヴァ近郊のラハヴキブツは、現在13℃。これでも実はとても寒いほうに入ります。いつもは日中20℃近くまで上がります。現在東京は4℃。冬の間は、日本の温度プラス十度と考えてよいでしょう。とても過ごしやすいところです。夏はこれから経験することになりますが、イスラエル人いわく「とてつもない熱さ」(暑いではなく熱いというニュアンス)ということです。 これからイスラエル、キブツの体験を綴っていくことになりますが、七月十三日まではイスラエルに滞在することになるので、現在進行形の部分と記憶をたどる部分が混在することになります。この体験記ではできるかぎり時系列に沿って書いていこうと思います。キブツの生活が中心になりますが、キブツには行かないけどこれからイスラエルを旅行してみたい、そういう方のためにも有益な情報が提供できればいいなと考えています。現地情報みたいなものですね。もしこれからキブツ、イスラエルに来たいと思っている方で、もし何か訊きたいことがあればワールドビュウの担当者を通じて連絡をください。僕にわかることであればお答えします。 キブツ体験記01『出国前夜、出国当日』 十月五日の夜に成田空港から日本を発った。前々日には東京に住む先輩の家に泊まり、一緒に現地の料理を扱ったレストランに食事をしに行くことになっていた。三日の夜にはアラブ料理、四日の夜にはイスラエル料理を食べに行く予定だったが、前者は臨時休業で食べることができなかった。イスラエル料理専門店は一つしかないみたいなので、名前を挙げるけれど『シャマイム』というお店です。江古田にあります。とても美味しいイスラエル料理を、リーズナブルな価格で腹いっぱい食べることができる。このとき食べたフムスとアラビックコーヒーに後に熱狂的にはまることになるがそれはまたどこかで。 そのお店で働いているイスラエル人のTさんに「明日イスラエルに行くんです」と話しかけた。現在の治安、どこの地域が住みやすいか、買い物に出やすいところなどを教えてもらい、「家族がいるからもし困ったら連絡して」と連絡先までいただいた。興味本位でガザはどれくらい危ないか訊ねると、「ガザは危険すぎるし、イスラエル人は絶対に行かない。外国人もよく誘拐されているから本当に危険」とのこと。さらにガザから数十キロ圏内では有事が起こればミサイルが飛んでくるからそこは避けるようにとアドバイスを受けた。 一番気になるのはやはり、テロの多寡である。「ごくまれに起こることはある。それは本当に運が悪かったケースで、まず巻き込まれることはないと言ってもいいよ。今まで知り合いでそういうのに巻き込まれた人はいない。国境から離れていれば日本人が思っているほどイスラエルは危険ではないよ」と彼は言った(実際にその通りだった)。 出国当日、朝から雨がずっと降り続けていた。携帯電話を最低限のプランに切り替え、池袋のビックカメラで変換アダプタを買い、そこで先輩と別れ、成田空港に向かった。その間に友人・知人に「しばらく日本を留守にします。連絡先は以下になります」とメールを送った。まるで自分はこれから特別な体験をしに行くのだ、と宣言するように。 今回の旅は僕にとっては初めての異国体験と言っていいかもしれない。小学生のときに家族旅行でハワイに行ったことがあるが、ハワイはどこの店でも日本語が通じ、またパックツアーということもあり現地の人と話すこともなかった。中学生の時に僕が住む町の姉妹都市事業で中国に行ったこともあるが、これも現地の人とは話すこともなくずっと観光地をめぐっただけ。これらの渡航は異国体験というにはあまりにもツーリスティックなものだった。それから海外に行こうと思ったことはなく、十年以上パスポートすら持っていなかった。今回の旅はヨーロッパ旅行を兼ねている。ロンドン空港から飛行機に乗る。イスラエルからロンドンまでバックパック一つで、それも陸路で行こうと計画している。当初の計画では四ヶ月間イスラエルで過ごし、それから欧州を目指す予定だったが、大幅に計画が変わり、二月からキブツウルパン(語学訓練施設を持つキブツ)に移ることになっている。 家族と一番仲の良い友人に電話をし、よくわからないままに出国手続きをする。持ち込めるライターは機内手荷物に一つだけということだったが、預け荷物に一つ紛れ込んでいて、後で呼び出されて恥ずかしい思いをした。難しい手続きもなく無事に機内に乗り込むことができた。雨はとどまることなく強く降りつづけ、ガラス戸に音を立てて割れる。土砂降り雨の中、発光筒を振る空港職員の姿をしばらく眺めていた。さようなら、日本。 寝ようにも後ろで騒ぐ中国人が僕の座席を蹴りそのたびに起こされ(二回注意したが直らなかったのであきらめた)、ヘブライ語の入門テキストを読み、日記をつけ、ああ煙草が吸いたいともがく、その繰り返し。それに飽きると真っ暗な空を眺め、物思いにふける。 七月から九月の半ばまで岩手県の沿岸部でボランティア活動に参加していた。そこで知り合った被災者の方たちやボランティア仲間の顔が浮かんだ。彼らはどうしているだろう。自分には時間と余力があるのに、まだ続けようと思えば続けられたのに、海外に行っていていいのだろうか、日本が大変な時に。いや、しかし、俺はやるだけのことはやった、俺は俺の時間を進めなければいけない、区切りはいるのだ、そう自分を納得させようとした。以前付き合っていた恋人のことも頭に浮かんだ。彼女は沿岸部ではないけれど岩手県に住んでいた。震災から間もなく別れることになり、それからは一度も会っていない。奇しくも十月五日は彼女の誕生日でもあった。 ウズベキスタンのタシュケントで乗り換えることになっていて、フライトチケットには午前二時とある。六時間で着くはずなのにまだ着陸する気配がないな、遅れているのかな、早く煙草吸わせてくれー、と苛立っていた。チケットの出発時刻は各空港のある時間に合わされているがそんなことすら知らなかったのだ。タシュケントで乗り換えイスラエルへ。 乗り換えた飛行機でも寝ることはできなかった。驚くことに乗客のほとんどが若者なのだ。それも仲良しグループらしい。ウェイトレスを呼びつけるようにキャビンアテンダントに何度もワインを求め、ごくごくと飲んでは大笑いをする。カップルも多く、飽きないほどさまざまな種類のキスを観察した。 後で知ることになったが、兵役を終えたイスラエルの若者は一斉に海外に飛び出してしばらく旅行を楽しむということである。こちらに来てから日本に数ヶ月滞在していたことがあるというイスラエル人に会ったことがある。彼はほとんど金を使い果たしようやく日本にたどり着き、お金をためてそれからイスラエルに帰ったと言った。「そんなすぐに仕事を見つけられたんですか?」と尋ねると、「ジュエリーを売っていたんだ」と彼は言う。一昔前、東京大阪の路上でまがい物の宝石を売っている露天商の若者はイスラエル出身だ、などという噂があったけれど、案外本当のことかもしれない。 着陸時刻を過ぎても機体は降りる気配を見せない。水の中に顔をうずめて話しているような声のアナウンスが続く。いったいどこの国の言葉なのかもわからない。そして突然の急降下。一瞬尻が浮き、遊園地のフリーフォールを思い起こす。客席の処々から悲鳴が上がる。それまでパーティーのような盛り上がりを見せていた客室内も一気に静まり返る。僕はきょろきょろと周りをみわたし、これはどうも怪しい雰囲気だなと察する。航空事故で死亡する確率は、車に乗って死亡する確率の何十分の一程度であるという言葉を思い出し、大丈夫だと自分に言い聞かせる。 結局機体は二周旋廻して無事に降り立った。機体が完全停止する前に「シャーローム、シャーローム♪」と二列前に座る二人の女の子が歌いだし、まわりの若者も「シャローム!フォー(歓声)」と呼応する。空飛ぶパーティー会場は大盛り上がり。僕が機内で読んでいた初級ヘブライ語のテキストには「イスラエルで便利な挨拶はシャロームです。これは平和・平和という意味です」とあり、なるほどまさにうってつけの場面だと思った。これは、僕が聞いた初めてのヘブライ語であった。 キブツ体験記02『キブツの登録のあれこれ』 機内パーティーも終焉を迎え、飛行機を降り入国手続をする。僕はほとんど英語ができないため、「わかりません」、「もう一度おねがいします」を繰り返し、呆れ顔され最後に名前と生年月日をもう一度復唱するだけでゲートを通してもらうことができた。どの本にもイスラエルのベングリオン空港は世界一厳しいと書かれていたが、ぜんぜん余裕じゃないかと思ってもう一度ガイドブックを読み直すと、それは"出国"手続においてであった。これを書いている現時点ではイスラエルから他国に空路で出たことはないので、どれくらい出国手続が厳しいかはわからない。ちなみにヨルダンへの陸路越境はとても簡単だった。 空港を出た瞬間に感じたことは、空気の乾燥である。そして暑い。上着を脱ぎ袖をまくり上げ、もらった地図を眺める。最初の目的地であるキブツオフィスは空港のマークからそう遠くないところにがあるため、僕は歩いていける距離くらいに思っていた。しかしよく見るとそれはベングリオン空港ではなく国内線の別の空港であった。地図を読んでいると、イスラエル人の女性が「May I help you? Are you Korean?」と話しかけてくる。拙い英語で行き先を告げると、丁寧に教えてくれ、おまけに電車のホームまで連れて行ってくれた。 電車に乗りこむとまず目に映ったのは、銃を持った兵士の姿である。それもハンドガンではなく大きなライフルやマシンガンを肩から吊るしている。各車両に三四人ずつ乗っていて、銃口を床に垂らしている。若々しい顔と無骨な銃がみょうに不釣合いだった。兵士の乗降は頻繁で、電車を降りたかと思うと、また別の兵士のグループが乗り込んでくる。どこかの国の要人が訪れているのだろうか、と思ったものだが、数日もすればこれが当たり前の風景になってしまう。むしろ彼らのおかげで都市型犯罪、テロに対する抑止力が働いていると思われる。 駅を降りてからタクシーでまずホステルに行き荷物を降ろし、必要書類を持ってキブツのオフィスに向かう。テルアビブ以外でもそうだけど、イスラエルの住所表記は日本と違ってかなりきっちりしたもので、見つけるのに大した苦労はない。それぞれのマンションやビルに番地表示板が見やすい位置に貼られている。「6, Frishiman」と書かれていれば、フリッシュマン通りの海岸側から六つ目の建物ということになる。とても簡単である。予約してもらった「ハヤルコン48」ホステルは、ハヤルコン通りの48番目の建物ということになる。 キブツオフィス(正式にはKibbutz volunteers Program Center。略してKPC)に入り、必要書類を渡すと、「食肉工場はどう?」と女性は単刀直入に言う。「他にはどういう仕事がありますか?」と僕は訊き返した。「あいにく、今はそれしかないの。空きがあるキブツは一つだけ。簡単な仕事よ、パッキングとかだから特に難しいことはないわ」 「それなら特に問題はないと思います」 これは事実と大きく異なっていた。ラハヴミートファクトリーは国内すべてのキブツの中でももっとも過酷な場所である。それはまたいずれ書きます。 彼女は電話を掛けはじめる。「キブツのマネージャーも了承したわ。あなたの行くキブツはベル・シェヴァ近くのラハヴキブツ。今日ここに来た韓国人の男の子もあなたと同じキブツに行くことになっているわ」 行き方を教えてもらう。セントラルバスセンターの6階から出ている369番バス。運転手にこの紙を渡して「Dvir(ドゥヴィール)ジャンクションと言えば降ろしてくれるわ。明日はシャバットで午後はバスが停まるから早めに行くのよ」と言われる。紙にはLahavというキブツの名前とマネージャーの氏名・電話番号が書かれている。大事にしまいこんでホステルに戻った。 と、こうして文章に起こすとスムーズに行われたように思われるが、僕は英語の聞き取りがほとんどできないので、何度も聞き返し、こちらの言っていることは伝わらずところどころ紙に書いて伝えた。オフィスもそういう外国人がボランティアとして来るのは慣れているからもしあなたが英語がほとんどできないとしてもおそらく大丈夫です。 キブツの選択について、ここでまとめて書きます。僕のように選択肢が一つしかない場合もあれば三つ四つある時もある。僕は知らなかったのだけれど、二七二のキブツのうちボランティアを受け入れているのは十分の一ほどしかない。場合によってはボランティアのいないキブツを薦められることもある。アドプテーションと呼ばれている(キブツ住人の家庭に子供として入る。もちろん正式な養子ではない)。滅多に提案されないことなので今回は割愛します。ちなみに、選択肢がない、あるいは自分の希望に沿わない場合、待つことも可能。個々のキブツへの登録はいつでもいいので、どこか旅行をしながらKPCからの連絡を待つというのも手ではある。しかし現在キブツにいながら異動の希望を出しているボランティアも多々いるため、待てば必ずしも上手くいくとは限らない。やはり時と場合による(つまり運)。後からキブツ内で仕事を変えること、キブツ自体を変えることも可能なので、どうしてもできないことでないかぎりとりあえず乗っかってみるというのをオススメします。 キブツ体験記03『テルアビブの夜』 キブツの登録を終えカメラを持ってテルアビブの街を歩く。まず海岸に出た。十月だというのに多くの人が海水浴、日光浴を楽しんでいる。昨日まで日本にいてだんだん寒くなってきたなと思っていたら、一気に地球が反対周りをして季節が戻ったような感覚。  海岸線を歩く。バトミントンをしているカップル、ビーチバレーをしているグループ。ただ海に向かってボールを蹴っては泳いで取りにいく、ただひたすらそれを繰り返す青年。赤く染まった沈みゆく太陽をのんびり眺めている中年カップルもいる。ときどき立ち止まり写真を撮る。少し進んだところで後ろから「ヘイ、ボーイ」と女の子の声がする。「ヘイ、ユゥー」とさらに大きな声がして振り向くと二人組みの女の子がこちらに歩いてくる。ボーイ? 俺のこと? と訝りながら返答すると、「あなた日本人でしょ」と訊かれる。「それで私たちの写真を撮ってくれない?」と彼女たちは僕の胸元を指さす。「いいですよ」と写真を撮る。「この写真はどうすればいいの? メールで送りましょうか?」と訊ねると、「だいじょうぶ。取っておいて。プレゼント。ところであなたいくつ?」と言う。二十六だと答えると、二人は顔を見合わせて驚く。僕のことを十八歳だと思ったらしい。二人は二十歳と二十一歳。覚えたての「レヒトゥラオゥト」(さようなら)と言って別れる。
海岸線を歩く。バトミントンをしているカップル、ビーチバレーをしているグループ。ただ海に向かってボールを蹴っては泳いで取りにいく、ただひたすらそれを繰り返す青年。赤く染まった沈みゆく太陽をのんびり眺めている中年カップルもいる。ときどき立ち止まり写真を撮る。少し進んだところで後ろから「ヘイ、ボーイ」と女の子の声がする。「ヘイ、ユゥー」とさらに大きな声がして振り向くと二人組みの女の子がこちらに歩いてくる。ボーイ? 俺のこと? と訝りながら返答すると、「あなた日本人でしょ」と訊かれる。「それで私たちの写真を撮ってくれない?」と彼女たちは僕の胸元を指さす。「いいですよ」と写真を撮る。「この写真はどうすればいいの? メールで送りましょうか?」と訊ねると、「だいじょうぶ。取っておいて。プレゼント。ところであなたいくつ?」と言う。二十六だと答えると、二人は顔を見合わせて驚く。僕のことを十八歳だと思ったらしい。二人は二十歳と二十一歳。覚えたての「レヒトゥラオゥト」(さようなら)と言って別れる。海岸線を突堤のあるところまで歩き、それから内側に入って、通りを縦横じぐざぐに歩く。両替商、食糧雑貨店、寿司バー、楽器屋、携帯電話ショップ、ピタサンド屋、書店、ブティック、ミシン屋、ストリップ、何でもある。Wi-Fiはどこでも拾える。オンに切り替えると画面いっぱいに発信先が表示される。もちろん日本でも同じようにたくさんWi-Fiは飛んでいるけど、驚くことにそれらはほぼすべてフリーなのだ。これは後に行ったエルサレムなど他の都市でも同じである。イスラエルについて、"先進国と言える"と書いている本をいくつも読んだけど、そのとおりだと思う。 明日困らないように、バスセンターを今日中に探しておくことにする。ベン・イェフーダ通りをまっすぐ行くとアレンビー通りにつながる。この二つの通りはもっとも人々の往来が盛んだ。アレンビー通りにあるカルメル市場の広場では音楽に合わせて多くの人がダンスを楽しんでいた。立ち止まって煙草を吸っていると、食べ残しを集めたナイロン袋を持った浮浪者の老人が「シガリア、シガリア」と煙草を吸うジェスチャーをまじえて言う。煙草をあげるとhappy day! happy day!と叫ぶ。思わず笑ってしまう。 歩き疲れたので、ベンチに座って通りを歩く人々の様子や清掃員の仕事ぶりを眺める。ふとあることに気づく。公共の清掃に従事しているのはすべて肌が黒い。海岸を歩いているときにも黄色いチョッキを着た清掃係をたくさん見かけたけど、肌が黒くない人はいなかった。こんな仕事嫌で仕方がないと言った風で、やる気の無さがにじみ出ている。地べたに腰掛けて休んで煙草を吸い、その吸殻をポイ捨てして去っていったりする。ただ清掃員の数は多いから通りは清潔に保たれている。日本と違い、人々は煙草をポイ捨てするのが普通でゴミも当たり前のように放っている。 近道しようと早めに曲がったところで通りの雰囲気が違うことに気づく。小便臭い。街灯はなく、大通りの照明でなんとか道が見えるくらいだ。目が暗闇に慣れてきて、さらに驚く。廃墟の一角がまるで蜘蛛の巣にかかったように、まるごと有刺鉄線でぐるぐるに巻かれている。アパートの上階から窓枠ごと落下して無残に散らばったガラスの破片。何年も前から放置されている車はもぬけの殻状態。建物の壁にもたれかけて地べたに座っている人々はすべて肌の黒い人々だった。僕が横を通りかかると話をやめ、じっと眺めてくる。華やかな大通りから一歩踏み入れただけで、がらっと変わる。昨今イスラエル国内で格差是正を訴えるデモ活動(主にアラブ系イスラエル人とのこと)が盛んになっている。これらの二つの出来事はこの国が内包する問題の一片を示していると僕は考えているけど、ここでの言及は避ける。  バスセンターに着く。最初そこがバスセンターとはわからなかった。垂直方向に伸びた大きな建物。ショッピングセンターかスタジアムに見える。見上げると建物から上方から車道が斜面になり、平地に向かって伸びている。KPCでもらった封筒に六階と書かれていてことを思い出す。ぐるりと外周を回る。入口は人ひとりが通れるだけの広さで、その前では警備員が客のバッグの中身を確認し身体を金属検知器で撫でている。
バスセンターに着く。最初そこがバスセンターとはわからなかった。垂直方向に伸びた大きな建物。ショッピングセンターかスタジアムに見える。見上げると建物から上方から車道が斜面になり、平地に向かって伸びている。KPCでもらった封筒に六階と書かれていてことを思い出す。ぐるりと外周を回る。入口は人ひとりが通れるだけの広さで、その前では警備員が客のバッグの中身を確認し身体を金属検知器で撫でている。そこで引き返しホテルの手前の角にあるカフェに寄った。カフェと言っても食料雑貨店が外にテーブルを出していると言ったほうが正しい。こういった形式の店が多い。客は店で缶ビールを買いそれを店外にあるテーブルで飲んでいる。客同士はほとんどが顔見知りのようで、やあやあと声をかけて入ってくる。僕は少し離れたところに置かれたテーブルに腰掛ける。500ml缶ビールは15シェケル、ピタサンドが18シェケル(この時期のレートは1シェケル=22円)。ピタは一番小さいサイズだったが物価を考えれば仕方がない。もう一本ビールを買い、ホテルに持ち帰った  ベランダでビールを飲みながら、日記を付ける。とても暑い夜だが、気持ちいい。ビールが格別にうまい。街の明かりに赤く染められた空。周りの建物に切り取られた視界から通りのほうを時間が経つのを忘れるほどじっと眺めていた。ビルに囲まれたスペースでは猫たちが喧嘩をしている。隣のビルはアパートで奥さんが旦那に大声でわめきちらしている。何度も行き交うヘリコプター。他のホテルやアパートでは僕と同じようにベランダでビールを飲んでいる人たちがたくさんいた。五分以上ずっとキスをしているカップルの姿も見えた。ヘブライ語と思しき音楽を爆音でかけながら走る車。鳴り止まないクラクションの洪水。それら細部の積み上げが異国にいることを知らしめる。 こうしてイスラエル初日、テルアビブの夜は淡々とふけていった。 キブツ体験記04『キブツに着く』 目覚まし時計より早く目覚める。飛行機でもほとんど寝ず前日もずっと歩き回っていたにもかかわらず気持ちよく目覚めることができた。身体が新しい刺激を受け、さらに刺激を求めているのか、不思議と疲れは無かった。 バスセンターに着き公衆電話からマネージャーのロニーに電話をかける。電話機の調子が悪く繋がった瞬間に落ちる。やっとつながり相手の声が聞こえたと思ったらまた落ちる。残った最後の1シェケルで「これからバスに乗ります」と伝え、相手の返事もぼそぼそとほとんど聞えないまま日本人にありがちなOKを繰り返し、着いたらまた電話しますと答えたところで電話が切れた。これが僕の人生で初めて英語で電話をした機会である。今でも思うけど、外国語で電話をするというのは緊張しますね、ほんと。 バスの運転手にDvirジャンクションと書かれた封筒を見せると、「一番前に乗りな。着いたら教えるから」と言われる。どこから来たんだ、何しに来たんだというようなことを訊かれたが何度も質問を訊きかえし、しどろもどろになって答える。最後に「ふむ、君の英語はまだまだだな。もっと勉強しなさい」と笑われる。コミュニケーション能力の不足をあらためて感じる。バスにもたくさんの兵士が乗車していて、ローテーションでどんどん入れ替わっていく。  バスはテルアビブから郊外へと走り始める。三十分もしない間に建物がぐんと少なくなり、一時間で車と道路だけという風景に変わる。イスラエルは大きく分けて四つの地区に別れていて、中部から北部にかけての砂漠・荒野から成るもっとも広い地域はネゲヴと呼ばれている。バスは幹線道路の近くの町に入りそこで客を拾いまた幹線道路に戻るということを繰り返す。バスに乗って一時間半、同じ風景があまりにつづくため眠くなりうとうとしていたところで運転手にここだと言われ降りる。
バスはテルアビブから郊外へと走り始める。三十分もしない間に建物がぐんと少なくなり、一時間で車と道路だけという風景に変わる。イスラエルは大きく分けて四つの地区に別れていて、中部から北部にかけての砂漠・荒野から成るもっとも広い地域はネゲヴと呼ばれている。バスは幹線道路の近くの町に入りそこで客を拾いまた幹線道路に戻るということを繰り返す。バスに乗って一時間半、同じ風景があまりにつづくため眠くなりうとうとしていたところで運転手にここだと言われ降りる。バスが去り目の前に現れたのは小さなカフェとコンビニとガソリンスタンド、それと不自然に広いがらがらの駐車場。雰囲気としては山間部の高速道路のパーキングエリア。キブツはいったいどこにあるんだと疑問に思う。ともかく電話をかけないといけないから店に入る。店員にラハヴキブツというのはこのあたりにありますか?と訊ねると、ボランティアで来たのかい?と言われ、そうですと答える。すると彼は電話をかけはじめる。「もうじき来るからここで待っていなさい」と言う。たまたま知り合いなのかと思ったがそうではなく、ボランティアがこのガソリンスタンドの清掃の仕事を受けていると後で知った。二十分ほどして男が現れる。彼は英語はできるかと訊ねる。「少しだけ」と答えると、ふーむ、とやや呆れ顔をされる。このロニーという男については今後さまざまな問題に悩まされることになる。何度もこの体験記で触れると思う。  車は幹線道路から垂直方向に唯一の道を進む。見渡すかぎり岩肌が剥き出しの荒野をしばらく走る。会話は無い。アップダウンがつづきいったいこんなところに人が住んでいるのか、と疑問に感じはじめる。水はどこから取っているのだろう。十キロほど走ったところで小高い丘の上に大きな集落が見える。もちろん下から見たのでどれくらい広いかはわからない。金網には電流注意の表示があり、何百メートルにも渡って張り巡らされているようだ。門は頑強なもので管理人が入ってくる車を監視している。これはどこのキブツでも同じである。この体験記でも「キブツ内では危険に感じることはなかった」と多くの方が書かれていたが、たしかに安全に関しては注意が十分に払われている。
車は幹線道路から垂直方向に唯一の道を進む。見渡すかぎり岩肌が剥き出しの荒野をしばらく走る。会話は無い。アップダウンがつづきいったいこんなところに人が住んでいるのか、と疑問に感じはじめる。水はどこから取っているのだろう。十キロほど走ったところで小高い丘の上に大きな集落が見える。もちろん下から見たのでどれくらい広いかはわからない。金網には電流注意の表示があり、何百メートルにも渡って張り巡らされているようだ。門は頑強なもので管理人が入ってくる車を監視している。これはどこのキブツでも同じである。この体験記でも「キブツ内では危険に感じることはなかった」と多くの方が書かれていたが、たしかに安全に関しては注意が十分に払われている。やや広めの道が長く伸び、そこを幹に枝葉のように各建物が広がっている。やしみたいな巨大な木(イスラエルではありふれたもの。名前は失念)が等間隔に生えている。ダイニング、ランドリー、マーケットの場所を教えてもらう。その後ろを取り巻くようにフラットがたくさん並んでいる。道には子供たちが忘れていった三輪車があり、犬がそこらじゅうで昼寝をしている。部屋に到着する。部屋は西洋風といったところ。衣装棚、テーブル、冷蔵庫、ベッドが二つ。ロニーが今日来る韓国人の男の子がルームメイトだと言う。彼は四時ごろ来るとのこと。僕は今まで実家から出たことがないし、ましてや他人と一緒に暮らしたことなんてないから、とても不安に感じる。さてどうなることやら。 キブツ体験記05『キブツの食事について』 ロニーの案内でボランティアスペースに行く。ひと気は無く、他のボランティアは二時半まで仕事をしているとのこと。TVルーム(ここが主にみんなで話をしたり映画が観たりする。共有PCもある)で一人ソファーに座っていると、一人の男の子が現れる。「ホゼと呼んでくれ。よろしくね。といっても来週で僕は国に帰るんだけど」と彼は言う。彼はグアテマラ出身でここのキブツには三ヶ月いて、ここ数日は仕事を終えて帰国まで仕事がないのだと言う。 話していると二人のインド人が現れる。僕は英語を話すのが得意でないから何度も聞き返すことになるけど、と言うと、「問題ないよ。この前帰ったドイツ人の男は最初ほとんど話せなかったけど三ヶ月ほどしたらぺらぺらになったから」と言う。ちなみにいうと、これは人によりけり。これを書いている僕は滞在が四ヶ月を超えたけど、しょっちゅう言葉に詰まる。ただ相手の言うことはまずまず聞き取れるようにはなったから、会話には大きな支障がない、その程度である。  部屋に戻って衣服の整理をし買い足すものを考えていると、誰かが部屋をノックする。出てみると女の子が二人いて一緒にダイニングに昼食を食べに行こうと誘われる。ブラジルとアルゼンチン出身。ホゼをくわえ四人でダイニングで食事をする。
部屋に戻って衣服の整理をし買い足すものを考えていると、誰かが部屋をノックする。出てみると女の子が二人いて一緒にダイニングに昼食を食べに行こうと誘われる。ブラジルとアルゼンチン出身。ホゼをくわえ四人でダイニングで食事をする。食事についてもっと詳しく書こう。白米は毎回出されているがやや油っぽい。イスラエル人、外国人ボランティアはあまり米を食べないから、だいたい残されている。肉は鶏肉が主に出され、ローストチキンとスニッチャー(カツレツ)は毎食置かれている。牛肉も週に二回は並べられる。魚はフライにされたものがたまに出るだけ。サラダはいろんな種類が揃っているがやや油が多い。これらは外で食べてもそんなに変わらなかった。イスラエル料理は、塩分は普通だが油はかなり多めである。そしてフムス。これはイスラエル・アラブ諸国の食事には必ず出る。ひよこ豆を炒ってペースト状にしたもの。単体で食べるということはなく、何かに付けて食べる。何にでも合うから不思議。パンにつけてもいいし、ご飯に乗せてもいける。ドレッシングのかわりに野菜につけてもいい。僕はほぼ毎日食べているが、いまのところ飽きていない。日本人にとっての白米と同じ位置にある食べものといえる。  エビ、豚肉は出ない。これはキブツでもレストランでも同じ。コシェルというユダヤ教の摂食戒律のためである。長くなるので割愛します(ネットですぐに見つかります)。コシェルは敬虔なユダヤ教徒には最も重要なルールの一つで、敬虔でないユダヤ人や外国人にはどうでもいい、というルールである。いろいろ聞いてみると豚肉はわりと食べているようである。聖地エルサレムや宗教的な都市では、どこの店の看板にもコシェルの規定に基づいているかどうかがはっきり書かれている。マクドナルドやドミノピザなどのチェーン店でも同じ。
エビ、豚肉は出ない。これはキブツでもレストランでも同じ。コシェルというユダヤ教の摂食戒律のためである。長くなるので割愛します(ネットですぐに見つかります)。コシェルは敬虔なユダヤ教徒には最も重要なルールの一つで、敬虔でないユダヤ人や外国人にはどうでもいい、というルールである。いろいろ聞いてみると豚肉はわりと食べているようである。聖地エルサレムや宗教的な都市では、どこの店の看板にもコシェルの規定に基づいているかどうかがはっきり書かれている。マクドナルドやドミノピザなどのチェーン店でも同じ。僕は食事に関してこだわりがまったくないから特に問題はなかった。油を摂ると腸がすぐにやられるため日本にいるときと同じく野菜ばかり食べて過ごした。ラハヴキブツにいた四ヶ月のあいだ魚は一度も食べなかったし、牛肉も二三回食べただけ。そういえば最初の一、二週間、無性にラーメンが食べたくなるときがあった。海外旅行に行った友人からも同じようなことを聞いたことがある。ラーメンに関してはあきらめてください。インターネットで探したし大きな街に出るたびにラーメンを出している店を探してみたが見つけることはできなかった。今でもあきらめていないけど、日本に帰ったときのお楽しみとして待つことにしている。 キブツ体験記06『ボムシェルターはダンステリア』 夕方になり韓国人のルームメイト(名前はカン)が到着する。とてもまじめで育ちの良さそうな身なりと髪型をしていて、大きな黒縁のメガネをかけている。この後たくさんの韓国人と知り合ったが、全員大きな黒縁のメガネをかけていた。韓国ではトレンディーらしい。部屋のルールについては、僕は他人と一緒に暮らしたことがないからほとんど任せるよと言った。彼は兵役時代にたくさんの人と寝食をともにし、大学のときにもルームシェアをしたことがあるという。彼は英語がほぼパーフェクトにできるから連絡事項の伝達などはとても助かる。 買い物を済ませたところで、別のボランティアが僕たちの部屋にやってくる。名前はヤン。チェコ出身。だいぶ前にあしらわれたと思しきコーンロウはうっすらと原型をとどめているのみで、そこに何本も太いエクステンションがつけられている。髭は二センチも伸びていて赤毛がまじっている。ヒッピーを現代に移植したらこうなるのではないかというような風貌だ。最初彼が話す言葉がとても英語には聞えなかった。どぎつい訛りがあり、ときどき吃音がまじる。まだ日が落ちていないのに赤ら顔。自己紹介をしたところで、これからクリケットをするんだけど来ないかと彼は言う。もちろん参加する。  四人のインド人、キブツニーク(キブツの住人)の老人、ホゼ、ルームメイトのカン。遅れてアメリカ人のジェイコブがやってくる。彼は「ヘイ、ガイズ。知ってるか? スティーブ・ジョブズが昨日死んだんだぜ」と言う。それから彼は自分の父親がスティーブ・ジョブズと一緒に仕事をしていただとか、父親は金持ちだとか、そういうことを話しはじめる。僕がふんふんと相槌を打っていると(あまりに早すぎてほとんど聞き取れなかった)、ヤンが「あいつが言うことはたいがい嘘だから気をつけろ」と耳打ちする。どうやらヤンとジェイコブは仲が悪いらしい。
四人のインド人、キブツニーク(キブツの住人)の老人、ホゼ、ルームメイトのカン。遅れてアメリカ人のジェイコブがやってくる。彼は「ヘイ、ガイズ。知ってるか? スティーブ・ジョブズが昨日死んだんだぜ」と言う。それから彼は自分の父親がスティーブ・ジョブズと一緒に仕事をしていただとか、父親は金持ちだとか、そういうことを話しはじめる。僕がふんふんと相槌を打っていると(あまりに早すぎてほとんど聞き取れなかった)、ヤンが「あいつが言うことはたいがい嘘だから気をつけろ」と耳打ちする。どうやらヤンとジェイコブは仲が悪いらしい。クリケットをして一気に彼らの輪に入ることができた。それ以来僕は新しいボランティアがやってくると、まず一緒にスポーツをすることにしている。言葉のコミュニケーションはたしかに重要だけど、言語だけがすべてじゃない。一緒に身体を動かすことでしか得られない連帯感もある。  みんなでダイニングに行き食事を取る。部屋に戻ろうとしたところでヤンが「今夜パーティーをするんだ。21時に1号シェルターに集合」と言う。しかし、21時に指定された小屋に行くと誰も来ていなかった。中に行ってみる。小屋に見えたのは実は階段の入口部分でしかなく、長い階段は地下室へとつながっていた。天井は低く、縦横6メートルの正方形、白地の壁には落書きがある。『会員制』というプレートを付ければ、悪い輩が集まる闇賭博所になるだろう。ヤンがオーディオ機器を担いで現れる。照明を赤色に交換し、七色のスポットライトをつける。ここはもともと何に使われてる部屋なんだい?と訊ねると、「ここはボム・シェルターさ。ここはギリギリ、ガザからのロケットの射程距離に入っているからね」と言う。「安心しなよ、この近くにロケットが飛んできたことは一度も無いんだ。いまはボランティアのためのパーティー会場さ」。
みんなでダイニングに行き食事を取る。部屋に戻ろうとしたところでヤンが「今夜パーティーをするんだ。21時に1号シェルターに集合」と言う。しかし、21時に指定された小屋に行くと誰も来ていなかった。中に行ってみる。小屋に見えたのは実は階段の入口部分でしかなく、長い階段は地下室へとつながっていた。天井は低く、縦横6メートルの正方形、白地の壁には落書きがある。『会員制』というプレートを付ければ、悪い輩が集まる闇賭博所になるだろう。ヤンがオーディオ機器を担いで現れる。照明を赤色に交換し、七色のスポットライトをつける。ここはもともと何に使われてる部屋なんだい?と訊ねると、「ここはボム・シェルターさ。ここはギリギリ、ガザからのロケットの射程距離に入っているからね」と言う。「安心しなよ、この近くにロケットが飛んできたことは一度も無いんだ。いまはボランティアのためのパーティー会場さ」。22時、ショットグラスに入ったウォッカで乾杯をしてミュージックスタート。大音量のクラブミュージックが流れる。ヤンはチェコでDJをやっていたと言う。閉じられたシェルターの分厚い鉄扉が振動し、外に出てみると丸聞こえで近くにたくさん家があるから大丈夫だろうかと心配したが、みんなは平然としている。どうやらよくここでパーティーをしているらしい。住人も慣れているのだろう。  四人のインド人うち最年長のクリスティが盆踊りのような奇妙なダンスをはじめ(まったく音楽のスピードに合っていないのが妙におかしかった)、他の三人もつられて“盆踊りダンス”をはじめる。昼食に誘ってくれた南米出身の二人の女の子はとくにノリノリで、ヤンと身体を合わせて踊る。アメリカ人のセイジュがくわわる。音楽のブレイク部分に合わせて笑い声が響く。
四人のインド人うち最年長のクリスティが盆踊りのような奇妙なダンスをはじめ(まったく音楽のスピードに合っていないのが妙におかしかった)、他の三人もつられて“盆踊りダンス”をはじめる。昼食に誘ってくれた南米出身の二人の女の子はとくにノリノリで、ヤンと身体を合わせて踊る。アメリカ人のセイジュがくわわる。音楽のブレイク部分に合わせて笑い声が響く。一息ついたところでみんなでシェルターの外に出て話をし、また地下におりて踊る、というのが夜中まで続いた。ホゼは「国は恋しいけど、こうしてみんなと踊れなくなるととてもさびしい」と言う。このパーティーは彼のグッバイパーティーをかねている。僕はもっぱら写真を撮り、酒ばかり飲んであまり踊らなかったけど、最高の夜になった。 キブツ体験記07『スローターハウス・ラハヴにようこそ』 パーティー明けの土曜日はキブツ内を散歩したりしてゆっくりと過ごした。イスラエルでは日本と一日ずれていて金・土曜日が休みで、日曜日から仕事がはじまる。イスラエルに来て次の日から仕事というのはなかなか大変なので、個人的には木曜日か金曜日にキブツに入るのをおすすめします。 ミートファクトリーの仕事は朝7時から。同じくミートファクトリーで働くイングリット(コロンビア出身)と待ち合わせて一緒に歩いていく。ジェイコブはどうしたんだろう? というとイングリットも「さあ」とすげなくこたえる。どうもジェイコブと他のボランティアとは人間関係に問題がありそうだ。 食肉工場はボランティアの居住するところから歩いて5分ほどの距離にある。本来はキブツの入口のほうまで回り道しなければならないが、それだとだいぶ時間がかかってしまうため、フェンスを越えて敷地に入る。工場の入口までの道はびっしりと豚の飼育小屋で埋められている。豚の鳴き声はしょっちゅう耳に入り、風向きによって臭いも運ばれてくるから豚がいることは知っていたし(それから毎晩午後十時半きっかりにその臭いに悩まされることになる)、僕がキブツオフィスで聞いたかぎりでは、食肉の加工・パッキングの仕事だということだったから、すでに“どこかで殺された動物”の肉をソーセージやその他の加工品にするのかと思っていた。 イングリッドに更衣室を教えてもらい、そこで白衣に着替え、キャップを着用する。イングリッドが工場長(以下ボス)に僕のことを紹介する。ボスは五十過ぎだが、多くのイスラエル人とはちがい肥えておらず、髪も生えそろっている。典型的なユダヤ人の顔をしたハンサムガイで若いころはとてもモテのだろう、そういう顔をしている。ユダヤ系アメリカ人作家のポール・オースターに似ている。 彼は一人のロシア人の若者のところに僕を連れていき彼に指示を出す。彼に命ぜられたのは段ボールを作る仕事だった。開いた段ボールを組み立ててガムテープを張る、そして積む。ただそれだけ。出荷用の段ボールは三つ。ボスは工場の中を忙しく動きまわり、イングリッドは別の部署だから僕は誰とも話すことなく、午前中はずっとその作業をしていた。 イングリッドからファクトリーのほぼすべての従業員は英語が喋れないとは聞いていた。困ったなあと思いながらもまあ少なくとも僕よりは英語ができるだろう、そう思っていたが彼らはまったく英語を解さない。英語が使えるのは数人のキブツニークの労働者(ボスもこのキブツの住人)だけである。いうわけでほぼすべてがボディランゲージで行われる。言葉がでてもそれがヘブライ語なのかロシア語なのかもわからないこともよくあった。数日して慣れるとこの二つの言語がまったく異なるものだということがわかったのだが、なにせヘブライ語を聞くのも、ロシア語を聞くのも初めてである。とはいえ、わかったところで聞き取れないことにかわりはなかったのだけど。 昼前にボランティアマネージャーのロニーが工場にやってくる。「書類をもらうのを忘れて。持っているか?」、「部屋にあります」、ロニーのバイクの後ろに乗って部屋に向かう。その途中でジェイコブが部屋の前の芝生に寝そべって日光浴をしている。 「仕事はどうした? ジェイコブ」 「What? 今日は休みだろ」 「何言ってんだお前」と言い、ロニーはちぇっと付け加える。 「アメリカは日曜日が休みだから勘違いしていた」とジェイコブはしれっと言う。 これはまあ嘘である。彼はもうここに来て一ヶ月半が経っているし、昨日彼は「明日から仕事がはじまるぜ」と言っていた。おそらく寝坊して行くのが面倒になりサボることにしたのだろう。悪びれた様子はまったくない。 昼食は45分、キブツのダイニングで食べる。四時に仕事は終わる。午前中に15分休憩が一回あるだけなので、丸々8時間働く。段ボールを置くスペースがなくなったところで、ロシア人の若い男がこっちへ来いと手招きをする。大きな鉄扉があり、4℃という表示板が張られている。冷蔵庫らしい。中には豚の開かれた体が所狭しと吊るされている。いつだったかテレビで牛が開かれて吊るされている状態を見たことがあるが、テレビで見るのと実際に見るのとでは大違いである。何よりにおいがある。奥に進んでいくと、豚の頭だけがまるで木に実がなったように一本の柱に吊るされていた。  「ゼッ!、ゼッ!、ゼ!(これを、こうして、こうするんだ)」と男は頭を一つつかみ、同じフックにかかっている長い舌を取り出し、それを大型の移動式トレイに投げる。頭がプラスチックとぶつかりどすんと音がする。空調だけの室内に硬い乾いた音がひびく。気持ち悪いなと思いながら豚の耳を掴んでトレイにどんどん放ってく。ここでジェイコブがやってくる。両耳に吊るされたイヤホンからは音が大きく外に漏れている。音楽に合わせて肩を揺らしながら歩いてくる。とても場違いに。ロシア人は指差しで同じことをやれと言うと、ジェイコブは英語でべらべらと男に何か言う。男は手を頭の横で振って(わかったから早くやれよという風にうんざりした表情を見せる)無視して、扉の外に出て行った。
「俺つかれてるんだ、お前やれよ。な?」とジェイコブは言う。
「ゼッ!、ゼッ!、ゼ!(これを、こうして、こうするんだ)」と男は頭を一つつかみ、同じフックにかかっている長い舌を取り出し、それを大型の移動式トレイに投げる。頭がプラスチックとぶつかりどすんと音がする。空調だけの室内に硬い乾いた音がひびく。気持ち悪いなと思いながら豚の耳を掴んでトレイにどんどん放ってく。ここでジェイコブがやってくる。両耳に吊るされたイヤホンからは音が大きく外に漏れている。音楽に合わせて肩を揺らしながら歩いてくる。とても場違いに。ロシア人は指差しで同じことをやれと言うと、ジェイコブは英語でべらべらと男に何か言う。男は手を頭の横で振って(わかったから早くやれよという風にうんざりした表情を見せる)無視して、扉の外に出て行った。
「俺つかれてるんだ、お前やれよ。な?」とジェイコブは言う。面倒だし、残り少なくなっていたから、一人でやる。元から一人でやるつもりだったのだ。ちょくちょく血が散ってくる。顔に散ってきたときはさすがに嫌だったが、もくもくと作業をつづける。 終わったところでジェイコブが「外に持っていけ」と言う。僕は一人で豚の頭が山積みになった500kgは超えているトレイ(バスタブより大きい。元レイカーズのシャックでも全身をつけることができる)を運ぶ。床は豚の体液や血でぬめっているため、なかなか進まない。そこでジェイコブが手を貸す。あまりにも非力。一人で押すのとまったくペースが変わらない。「おい、チャイニーズ。ちゃんと押せよ」と口だけはしっかり。 ジェイコブは一つの頭を取り上げる。「キスミー、キスミー」と豚の頭を自分の顔の位置に合わせてからかってくる。どっと疲労感が押し寄せる。これが毎日続くのかと思うと、うんざりしてくる。もちろんこの疲弊の根源はこの男である。 こうして僕の4ヶ月に渡る食肉工場勤めは幕を開けた。どうなることやら。 キブツ体験記08『ボランティアの仕事と数』 午後四時に初仕事を終えてボランティアスペースに戻る。ミートファクトリーの敷地を抜ける裏道は一本しかなく必ず通ることになる。驚いたことにみんなもう仕事を終えてくつろいでいる。インド人のアシシに何時に終わったのと訊くと二時半だよという。 毎日?――そうだよ毎日。いつから仕事がはじめるの?――だいたい朝七時半。ということは七時間?――だいたいそんなところかな、昼休憩入れて。 それから仲間たちに仕事の内容と時間を聞いたが、だいたい同じ。僕は朝七時から始まり午後四時まで。ということは二時間多い。少しして同じく工場で働くイングリッドもボランティアスペースに戻ってくる。労働時間について尋ねる。「そうなのよ。ミートファクトリーは長いの。でも他のボランティアと違って週に休みが二日あるから」と教えてくれた。マネージャーのロニーからは何も聞かされていない。この夜ロニーがボランティアスペースを訪れたため、彼にそのことを尋ねると「ミートファクトリーは、私が関知することはできない。休日の取り方もすべてあっちのマネージャー(ボス)に聞いてくれ」とのこと。それぞれの仕事によって管理が変わるようだ。 ここでボランティアの仕事を紹介します。それぞれのキブツによって仕事が変わることもあるが、他のキブツから移ってきた人から聞いた話、さらに僕が二つの目のキブツに来てからの情報も含めます。 ・キッチン……ダイニング内のキッチンで食事を作ったり、洗い物、掃除をしたりする。何百人も来るから大きな仕事だけど、機器が揃っているし、キブツニークの従業者も多くそこまで大変ではない。 ・ガーデン……キブツの清掃を行う。大きなトラクターの荷台に乗り、キブツ内の道を回りゴミを拾ったり、住人が庭仕事をして出た小枝などを拾う。引越しを手伝うこともある。あとは近くのガソリンスタンド(おそらく請負業務)の清掃に月に二三回行く。 ・ランドリー……キブツでは大きなランドリーがあり、住人たちがそこに洗濯物を持っていく。だからキブツには家庭用洗濯機というものはない。またいずれ詳しく書くけど、キブツにおけるランドリーは、ダイニングとならんでキブツ(ヘブライ語で「共有」という意味)の象徴的存在であった。ちなみにラハヴキブツではランドリーの仕事はなかった。 ・工場……ほとんどのキブツは工場を持っている。僕がいるラハヴでは二つ工場があり、メインがミートファクトリー、もう一つが金属加工工場。 これらの共通していること、それはすべて肉体労働ということ。ヘブライ語ができなければ体を使うしかない。まあそれは当然のこと。以前はベイト・ヤラディーム(「子供の家」。保育園とは違うが、現在のイメージとしてはそんな感じ)でボランティアが仕事があった。イスラエルに来る前に読んだいくつかの本の中ではボランティアの仕事ぶりが書かれていた。以前はラハヴキブツでも他のキブツでもベイト・ヤラディームでの仕事を任されたというが現在ではボランティアは仕事を任されていない。 ラハヴキブツではボランティアはそれぞれ、ダイニングに五人、ガーデンが二人、工場に三人に振り分けられていた。ボランティアの数によって振り分け人数は変わるが、割合はほとんど変わらない。僕が来たときボランティアは十人だった。僕が滞在した四ヶ月半でもっとも多いときが十五人。平均すれば十二、三人。これはキブツボランティアの数としては少ないほうで、他のキブツでは平均して十八人ぐらいが汗を流している。もっとも多くボランティアを持つヨートゥバタ・キブツ、ゲヴァ・キブツは常時三十五人(おそらくほぼ固定)。多いほうがいいのか少ないほうがいいのか、これは僕にはわからない。ただ僕のいたラハヴキブツではグループがなく、みんな仲が良かった。たぶんこれより多いと二つか三つにグループが分かれると思う。 やはり気になるのは男女比だろう。女の子の割合は3~5割を推移する。夏は女性が多くなるので女の子とはしゃぎたいという人は夏に来ることをオススメします。僕が来たとき女の子はイングリッドだけだった。僕がここに来た初日、イングリッドと一緒に声を掛けて来たブラジル人の女の子は、元ボランティアで現在はテルアビブで暮らしていてたまたま遊びに来ているだけだった。そのイングリッドも僕が来た一週間後にキブツを去った。そしてラハヴキブツ・ボランティアスペースは野郎どもの巣窟と化していく。 キブツ体験09『近くて遠い国のルームメイト』 
僕は26年間ずっと実家暮らしで一人暮らしをしたこともない。昨年震災の関係で岩手県の沿岸部でボランティアをしたがそのときは畳一枚分のスペースに寝袋を敷いて生活するというものだった。体育館に二百人が寝る。夜中はヒキガエルも驚きの大合唱だった。気の使うこともあったがボランティアはいちいち文句を言う立場でも無いことはほとんどの人がわかっていたし、特に問題は無かった。ルームメイトと一緒に住むというのは初めての経験だ。僕はなんとかなるだろうと思っていたが、こんなに大変なこととは思わなかった。相性というものがある。ルームメイトと友人は、まったく別のファクターで成立している。 ルームメイトのカンとは、仕事終わりによくバスケットをした。食事も一緒に取り、それからの時間はボランティアスペースで他の仲間たちと談笑し、部屋にもどるとお互いに語学を教えあった。彼は日本の文化・歴史についてよく知っていた。僕は彼に日本語を教え、彼は僕に韓国語……ではなく英語を教えてくれた。彼はとても流暢な英語を話した。「とにかく語学は使いつづけることでしか上手くならない」とよく言った。それからおやすみといってカンは寝る。楽しい時間はここまでである。僕らの問題はここからはじまる。 仕事の開始時間が違えば寝る時間はおのずと異なる。マネージャーのロニーの手際の悪さもあり、カンの労働場所は固定されず朝6時から仕事がはじまったり7時半からはじまった。さらに彼は必ず8時間は寝ないといけないという体質。僕は一日5時間ほどの睡眠時間で、寝るのは深夜1時半を過ぎてから。僕はなるべくカンが寝てからは部屋にいないように気をつかっていたが、23時半を過ぎるとボランティアスペースもからっぽになるため、部屋に戻って英語の勉強をしたり本を読んだりしていた。カンは異常なまでに音に敏感で少しの物音でも起きてしまう。イスが床を擦る音、トイレの水洗。30~45分に一度タバコが吸いたくなり、外に出ようとする。扉がゆがんでいてキーッと必ず音がする。僕は起こさないように数ミリずつじわじわと扉を開いて外に出ていた。一回の開閉に5分以上かかった。少し動かしてはカンの寝息を確認し、また少し開く。気分はまるでこそ泥である。さらに、彼は僕のいびきが大きいから枕を下げるように言った。それ以前も以後もいびきのうるささを指摘されたことはない。 「そんなに敏感だったら、兵役に就いていたときは苦労したんじゃない?」と尋ねたことがある。 「それは体を酷使していたから毎日すぐに寝付いていたよ。寝る時間も決まっていて、就寝時間が来ると強制的に電気を切られていたから。一人のいびきだとそのペースや乱れが気になる。多くのいびきが重なると、それはただの大きな音の塊として存在するだけだから問題なかった」とのこと。 これはわからないでもない。たとえばカフェで本を読むとする。隣に二人組みの客がいたら会話の内容が入って本に集中できないが、たくさんの客が固まって話をしていると、それはただの音の集合体である。とはいえ、僕にできることは何もなかったのだけれど。 ダイニングでは火・金曜日しか夕食が出ないので、各自の部屋(僕たちの部屋にはキッチンがあったが基本的にはない)、もしくはボランティアスペースにあるキッチンで各々作って食べる。昼食時に食事を弁当に詰めて持ち帰って食べることもできる(有料)。カンは料理が得意だった。僕は料理ができないため、洗い物・部屋の掃除をしたりして分担していた。睡眠以外にはまったく問題はなかった。でも睡眠は、厳密に言うとカンの睡眠はあまりにも大きな問題として僕らのあいだに横たわっていた。 僕はイスラエルで迎えた初めた週末をエルサレムで過ごした。その前夜僕らは睡眠についての話をしていた。そこから帰ると、残っていたメンバーがシェルターでパーティーをしていた。僕たちが戻ってそこに立ち寄ると、カンがちょっといいか?と言って僕を外に連れ出した。 「キブツを移ることになったんだ」と彼は言った。「誤解しないでくれよ。君が問題じゃない。まだ一週間だけど、ロニーはまったく僕の言うことを気にも留めていないんだ。まず次の日どこに行けばいいのかわからないし、連絡の不備も多すぎる。それにここのキブツは他とシステムが違うからお金もかかる」 「睡眠もその移る理由にある?」 「少しはあるかな、正直いうと」とカンは言った。「それは仕方のないことだよ。僕のわがままもあるかもしれない。人と暮らすのにあまり向いていないかもしれない。でもまだイスラエルに来て一週間だから別のキブツでもう一度試すよ。それでダメだったら仕方がない。僕のせいだ」 カンは二日後に去っていった。彼は三ヶ月別のキブツで過ごし、年明けに韓国にもどった。彼が移動してからも帰国してからもFacebookでよくやりとりをする。振りかえると、カンがキブツを移ったことは僕らの関係においては良いことだった。おそらくあのまま共同生活をつづけていたら僕らはほとんどいがみあっていただろうと思う。 僕らは来年の秋に韓国で会う約束をしている。マスメディアやインターネットの情報を見ていると、韓国は近くてとても遠い国に思える。対立している部分のほうについつい目がいってしまう。この後ラハヴで二人の韓国人と会った。彼らとも仲良くなった。話の中にお互いの国が抱える問題について話したこともあるし、そういう話は他の国の外国人とは持ち上がらない。それらは僕にはとても有意義なものだった。 とはいえ、やはり僕は思う、国同士がどうあろうが、僕は個人としてその人と付き合うだけなのだと。 |

